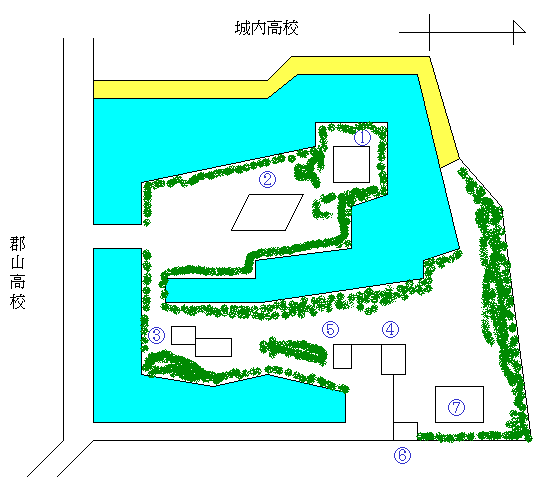昔は立派な天守閣が築かれていたそうですが、現在は天守台を残すのみ。北東には、薬師寺の塔が見えました。ちなみに、ここの石垣にはお地蔵さんも使われてしまったとのこと。逆さまにはまっているゆえ「逆さ地蔵」と呼ばれているそうですが、見忘れました(^_^;)
②柳澤神社
柳澤神社は明治13年に、本丸の敷地内に創建されたとのこと。祭神は江戸幕府五代将軍・徳川綱吉の治世に権勢を振るった柳澤吉保です。柳澤吉保というと、忠臣蔵などの話では悪役として描かれていることが多いですが、説明書によると(以下抜粋)
「御祭神吉保公の英智は群を抜き歴史上稀な出世をしたため妬を受けて悪い噂の主にされ善行を消され歴史を歪めて伝えられた事は残念な事です」
とのことでした。人は有名であればあるほど、よい噂もあれば悪い噂もあるもの。どちらの噂を信じるか、どちらが実像を表しているのか。それとも、両方とも真実なのか、両方とも虚偽なのか・・。
③柳澤文庫
毘沙門郭にたたずむ柳澤文庫は、財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会が昭和35年秋に設立した地方史誌専門図書館です。拙者は入りませんでしたが、古文書はじめ奈良県や柳澤家関連の一般蔵書を公開しており、歴史講座や古文書講座なども開いているそうです。
ちなみに、入館料は大人200円。
④追手門

現在残っている縄張りは秀長の頃のもの、とのこと。
⑤追手門向櫓

この日は曇り空でしたが、堀の水面は木々の葉をいっぱいに映して緑色でありました。春は桜も美しいそうです。
⑥追手東隅櫓
⑦市民会館
なんと、城の敷地内に市民会館がありました。瓦屋根にカーテン付ガラス窓という、歴史を感じさせる建物でありました。
現存している大和郡山城は本丸とその一部だけで、他は二校の高校、公園などになっております。黄色い部分は遊歩道となっております。ここから見える内堀は水枯れしており、石垣の間から植物が伸び放題でしたが、その深さはかなりのもの。水をはるよりも、空堀のままのほうがいいかもしれません。
城跡と思われる石垣は上の見取り図の外側にもあり、当時はかなり大きな構えの城だったようです。堀の周りの石垣には草が茂り、本丸跡の周囲は古城の雰囲気をかもし出しておりました。入城料などは必要なく、自由に見て回れます。 <交通手段>
・近鉄「郡山」駅から徒歩4,5分ほど。西大寺方面から来た場合は、電車から見えます。
・駐車場は追手門近くに数台分あり