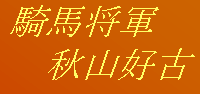
 |
幕末に生まれ、激動の明治時代を生き抜いた軍人・ |
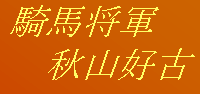
 |
幕末に生まれ、激動の明治時代を生き抜いた軍人・ |
秋山家は伊予国・松山久松家に仕えるお
伊予の言葉は日本で最も悠長な言葉といわれており、そこに暮らす人も穏やかな性格の人が多いという。好古も伊予人らしい穏やかな性格であり、およそ軍人として戦場に出て活躍するような型の人間ではなかったらしい。
この年、約250年続いた徳川幕府が崩壊。時代は大きく変化した。松山藩主の久松家は佐幕側の藩であり、長州征伐などにも加わっていた。そのため、維新後は南の土佐藩が伊予を制圧。久松家は15万両もの賠償金を背負わされてしまった。当然、藩財政は火の車となって倒れ、その藩士達の家の生計も苦しくなった。さらに困ったことに、秋山家ではこの年もう一人の男児が誕生した。のちに海軍に入隊、日露戦争では少佐の階級で連合艦隊司令官・東郷平八郎の頭脳としてバルティック艦隊迎撃の作戦立案を行った
お父さん、赤ん坊をお寺にやっちゃ、いやぞな。
追っ付け、うち(自分)が勉強してな、お豆腐ほどのお金をこしらえてあげるがな
陸軍学校時代、そしてフランス留学など、騎兵研究に没頭した好古であったが、その少年時代は経済的な理由で教育を受ける機会に恵まれなかった。松山藩には藩校・明教館があり、藩士の子弟は8歳になると、皆その藩校に通っていた。好古も例外ではなく、成績はかなりよかったらしい。しかし、その2年後には明治維新により藩が瓦解。秋山家の生計も苦しくなり、好古も生きるための労働に時を費やす日々を過ごした。
好古13歳の頃、、小学校が設立された。この小学校では、旧士族だけでなく町人の子弟達も入学することができたが、好古は入らなかった。理由の一つは、13歳という、小学校に入るには高い年齢。もう一つは経済的な理由である。のちに中学校もできたが、やはり経済的な余裕はなく、入学はできなかった。経済的に苦しかった秋山家だが、それでも旧士族の中ではまだいくらかましなほうであった。父・平五郎久敬は真面目を絵に描いたような男で、若い頃から徒士目付という役職についていた。「勤務態度は真面目に尽きた」という評判だったらしい。久松藩崩壊後、退職金として600円を受け取ったが、これから成長する子供を抱える秋山家にとっては微々たるものであった。多くの武士はこの退職金を元手に、農民になったり、あるいは商売を始める者などもいたが、久敬は何もしなかった。しかし、何もしない方がよかったかもしれない。商売を始めたものなどは、慣れない仕事に悪戦苦闘し、借財の山を築いて路頭に迷う者も多かった。その一方で、久敬は藩士時代の真面目な勤務態度をかわれて、県の小役人として採用された。薄給だったが、なんとか一家が食いつないでいくことはできた。しかし、子供を学校にやる余裕はなかった。
 |
 |
|
秋山兄弟の父・平五郎久敬と、母・お貞の写真。 (愛媛県立歴史民俗資料館蔵) |
明治政府は、国民達に学問を大いに奨励した。学問を身につけたものは国家が召抱えることを約束した。戦国時代は武勇で身を立てた者が多数出た時代だが、明治初期は学問で身を立てる時代といえるかもしれない。好古も学校に行きたかった。勉強したかった。が、勉強に必要な資金を用意することができなかった。
ただで学べる学校はないだろうか。
好古は切実にそう思った。そんな中、好古16歳の時、大阪に「ただで学べる」学校ができたという話が飛び込んできたのである。「一種名状しがたい哀しみがあった」
前述のように、大阪は教師が不足しており、この小学校の教師は校長先生一人しかいなかった。この野田小学校の校長は、妻が長州人であるというコネを使ってやってきた男だった。この校長は、自分のことはただの「校長先生」ではなく、「紅鳥先生」という雅号で呼べ、と好古に強要したらしい。「校長」も「紅鳥」も音は同じであるから、どっちで呼ぼうが違いはわからないと思われるが、これに何か意味があるのだろうか?また、好古が佐幕側だった伊予出身であることから、何かにつけて好古を「乱臣賊子」よばわりし、自分が長州側の人間であることを誇っていたらしい。妻が長州人であることだけで、紅鳥は自分に大義名分があると錯覚し、好古に対して優越感を感じていたようだった。しかし、この優越感も長くは続かなかった。
好古は生粋の日本人であったが、色白で、切れ長の大きな目を持っており、鼻が高く、日本人というよりは西洋人顔であった。実際、陸軍大学校に教師として招かれたドイツのメッケルは、好古を見て「君は西洋人か?」と尋ねた。通訳が「彼は生粋の日本人です。」と答えると、たいそう驚いたという話がある。もう一つ似たような話がある。日露戦争後、日本騎兵隊が兵学の研究対象として話題を集め、多くの西洋人武官が日本を訪れた。彼らの多くは「日本人にロシアのコサック騎兵を破れるわけがない。西洋人の顧問がいるに違いない。」と考えており、千葉の陸軍学校で指揮をとる好古を見て「やはり西洋人顧問がいた。」と信じて疑わず、誤解をとくのにたいへん苦労したという。
こんな西洋人顔の好古は美男子であり、故郷の松山や留学先のフランスではかなり女性にもてたという。しかし、当の本人は「男子に美醜は無用」という信念の持ち主で、ラブロマンスとは無縁だったようだ。自分が美男子だということを人に言われると、かえって不機嫌になるぐらいであったという。
上の写真は大尉の頃のもの。
(愛媛県立歴史民俗資料館蔵)