
大阪府箕面市 萱野三平邸・展示資料
萱野三平邸は1973年に大阪府の史跡指定を受けています。
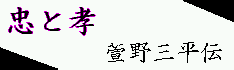
主君への忠誠と、親への孝行。二つの板ばさみに苦しみ、悲運の生涯を閉じた赤穂浪士。
こちらでは、忠と孝の板ばさみに悩み苦しんだ萱野三平重実を紹介いたします。

萱野家は源氏の流れをくむ一族で、鎌倉時代から摂津萱野郷を領した土豪の家だった。この地は西国街道に面しており、この街道に面して立派な武家屋敷を構えていたという。
戦国時代、萱野家は織田信長の配下である伊丹城主・荒木村重に所属していた。ところが、村重は信長に対して謀反を起こして敗北。萱野家も領地を没収されてしまう。時が流れて江戸時代になると、縁あって美濃出身の旗本・大嶋家に仕えることとなり、萱野家旧領付近の大嶋家の所領となっていた土地の代官を勤めることとなった。
三平は延宝3年(1675年)に、父・重利の三男として誕生した。13歳の時に父の主君・大島出羽守の推挙で浅野内匠頭に中小姓として仕えることとなった。中小姓は、主君の側用人のような役職だったらしい。
元禄14年(1701年)3月14日
浅野内匠頭刃傷事件
三平は、早水藤左衛門と共に主君の刃傷事件を赤穂に知らせる第一の使者となって、早駕籠に乗った。言葉で記述するのは簡単だが、この早駕籠の使者というのは命懸けのものだったらしい。乗り心地の良さなどは皆無であり、乗り手は振り落とされないように必死につかまっていなければならなかった。実際、彼と早水は途中で数回、駕籠から振り落とされてしまったらしい。それでも、この報はすぐに赤穂に知らせなければならなかった。刃傷事件となれば、お家取り潰しという処分も可能性がある。主家がお家取り潰しなるということは、赤穂藩士全員が所領を召し上げられ、浪人に身を落とすことを意味していた。彼らは不眠不休で155里(約600km)の道のりを突っ走り、驚異的な早さで3月19日未明に赤穂に到着。疲労困憊、息も絶え絶えの状態であったが、井戸水でわずかに一心地ついただけで、すぐに国家老(筆頭家老)・大石内蔵助良雄にこの凶報を伝えたのであった。
少々脱線するが、彼の人柄をうかがわせるこんな話が残っている。
早駕籠で赤穂へ急ぐ途中、西国街道沿いの実家の前を通ると、そこで母の葬儀が行われているのを目にした。母という存在は大きい。親不孝を自認し孝行などにまるで縁のない人間であっても、その母の死に際して心に悲しさを感じない、という者は一部の例外を除けばまずいない。ましてや、三平ほどの人物が、母の葬儀を目の当たりにして、後ろ髪を引かれることなしに振り切ることなどできなかったであろう。しかし、彼は重大な任務の途中であった。主家を失う悲しみの報告の上に、母を失った悲しみを背負って、一路赤穂に向かった、というのである。
さて、話は戻る。
同日の夜、第二報が赤穂に到着。
主君・浅野内匠頭は切腹だが、相手の吉良上野介にお咎めなし
という幕府の裁定が赤穂に伝えられた。喧嘩両成敗の慣習法を無視した処置だと赤穂藩士達は激しく憤り、籠城論、開城論、殉死論などが飛び交って混乱を極めたが、結局は無血開城となった。しかし、事件はこれだけでは終わらない。大石は藩士達を集めて自らの存念を語り、それに賛同する者から起請文を集めたのである。他の藩士達と同様に、幕府の処置に激しい憤りを覚えた三平も起請文を提出。大石の盟約に加わった。この時の盟約とはどのようなものだったのかははっきりしていないが、彼の胸中には「吉良邸討ち入り」があったのかもしれない。
4月下旬頃
赤穂開城後、三平は摂津・萱野郷の実家に戻った。
三平は討ち入りを急ぐ「急進派」であったという。急進派といえば堀部安兵衛を中心とする「江戸急進派」が最大勢力であったが、三平も同様に早期の討ち入りを唱えていた。しかし、その前に彼にはやり残していた大事なことがあった。母の供養である。6月28日、母の百か日の法要をとりおこない、葬儀に参列できなかった悔いを埋め合わせた。
母の供養も済ませた三平は、大石に討ち入りの決行を促すが、大石はうなずかなかった。この時はまだ主君・浅野内匠頭長矩の弟である浅野大学長広の処分が決まっていなかったのである。浅野家再興運動を進める大石から見れば、明らかに時期尚早であった。
9月下旬頃、大石は猛る三平をなだめ、説得するために、大高源吾を使者として派遣した。大高源吾は俳諧をたしなむ文化人でもあり、「子葉」という俳号も持っていた。討ち入り直前に吉良邸で開かれる茶会の情報を入手したのも彼である。三平もまた俳諧をたしなんでおり、「
なお、大高源吾は三平のみに限らず、その他の同士との連絡役として各地を飛び回っているた。
そうした中、三平の父・重利は、三平に「大嶋家への再仕官」を勧めたのである。実際、三平は美濃の大嶋家に数日逗留したこともあった。今の三平は浪人に過ぎない。簡単に言えば無職である。長く続けるものではない。仕官先を失ったら別の仕官先を探すことが、浪人侍の普通の身の振り方であった。また、大嶋家は戦国時代に土地を失った萱野家を返り咲かせた恩ある主君の家である。しかし、彼はすぐにこの話に飛びつくことなどできなかった。父に再仕官の口を見つけてもらうために、これまで浪人を続けたわけではない。浪人を続けていた理由は、もちろん来る「吉良邸討ち入り」のためであった。
三平には「忠」を重んじる心があった。俳句をたしなむ風情を知る心もあった。そして、「親孝行」の精神も持ち合わせていた。それだけに、父に薦められた再仕官の話を無下に断ることはできなかった。「忠と孝」。この両方をわきまえていた彼は、その両方の板挟みとなってしまった。父・重利は、息子が「吉良邸討ち入り」に参加する意志がある、ということを確信していたらしい。三平は「江戸に出て仕官先を探す」と言って、江戸へ向かう許可を父に求めたこと。世間では「いつ赤穂浪士が主君の仇を討つのか?」という噂が絶えなかったこと。父・重利は当惑した。今回の討ち入りはただ事では済まされない、ということは簡単に予想できた。討ち入りは、幕府の裁断に対する反抗、という一面が拭えない。勝っても負けても、罪を問われるのではないだろうか?親戚縁者に罪が及ぶのが当時の習わしであったし、場合によっては恩ある主家・大嶋家にも累が及ぶかもしれない。旗本である大嶋家の家臣の者から、討ち入り参加者が出たということで、罪を問われる可能性は十分考えられた。
三平の心は乱れた。
元禄14年 年末頃
説はいくつかあるようだが、この頃、江戸で高田郡兵衛が脱盟した。郡兵衛は堀部安兵衛と同じく、江戸急進派の一人であった。槍の実力はかなりのものであり、討ち入りに対して盛んに気焔を上げていた者である。その郡兵衛が脱盟した。脱盟の理由は「再仕官」である。あれほど討ち入りを盛んに急かしていた郡兵衛の脱盟に憤る同志は多く、堀部安兵衛などは郡兵衛を斬ろうとしたらしい。
三平が、郡兵衛脱盟の報を聞いたかどうかはわからないが、もし聞いていたのなら、これが彼の最期を決めた決定的な要因だったのかもしれない。
元禄15年 1月14日
萱野三平自害
この日は、月こそ違うが主君の命日と同日であった。三平は自宅の長屋、西の部屋で自害して果てた。
彼が自害という道を選ぶまでに、どんなことを考え、思い悩んでいたのだろうか。遺書は父と大石内蔵助宛てに、2通残した大石宛てのものには、同志達と共に約束を果たせない罪を侘び、そして討ち入りの成功を祈る旨を記したという。
俳人でもある彼の辞世の句は
晴れゆくや 日ごろ心の 花曇り
であった。
「心の花曇り」とは、彼の心に重くのしかかって消えない「忠と孝」の板ばさみのことだろうか。忠義の信念を貫けば、親兄弟に罪が及び、「孝」が立たない。だからといって、大嶋家へ再仕官すれば、それは結局は高田郡兵衛が選んだ道と同じものだった。「孝」を立てれば「忠」が立たなかった。
「日ごろ」とあるから、きっと来る日も来る日も悩んでいたのだろう。
そして、「晴れゆくや」。「死」という道を選ぶことで、来る日も来る日も彼の心に立ち込めた「花曇り」は、晴れ渡ったのだろうか。
吉良邸討ち入りに参加したのは、47名。討ち入りに至るまでに、多くの者が脱落していきました。脱落していった者たちは「醜夫」などと呼ばれ蔑まれていましたが、志半ばにて病死した岡野金右衛門(討ち入った岡野金右衛門の父。彼の名は「九十郎」だったが、無念の死を迎えた父の名を受け継いで、討ち入りに加わった。)、矢頭長助(矢頭右衛門七の父)、そして
参考資料
書物
「四十七人の刺客」
拙庵「歴史小説紹介の間」にあり。
史跡

大阪府箕面市 萱野三平邸・展示資料
萱野三平邸は1973年に大阪府の史跡指定を受けています。